top of page
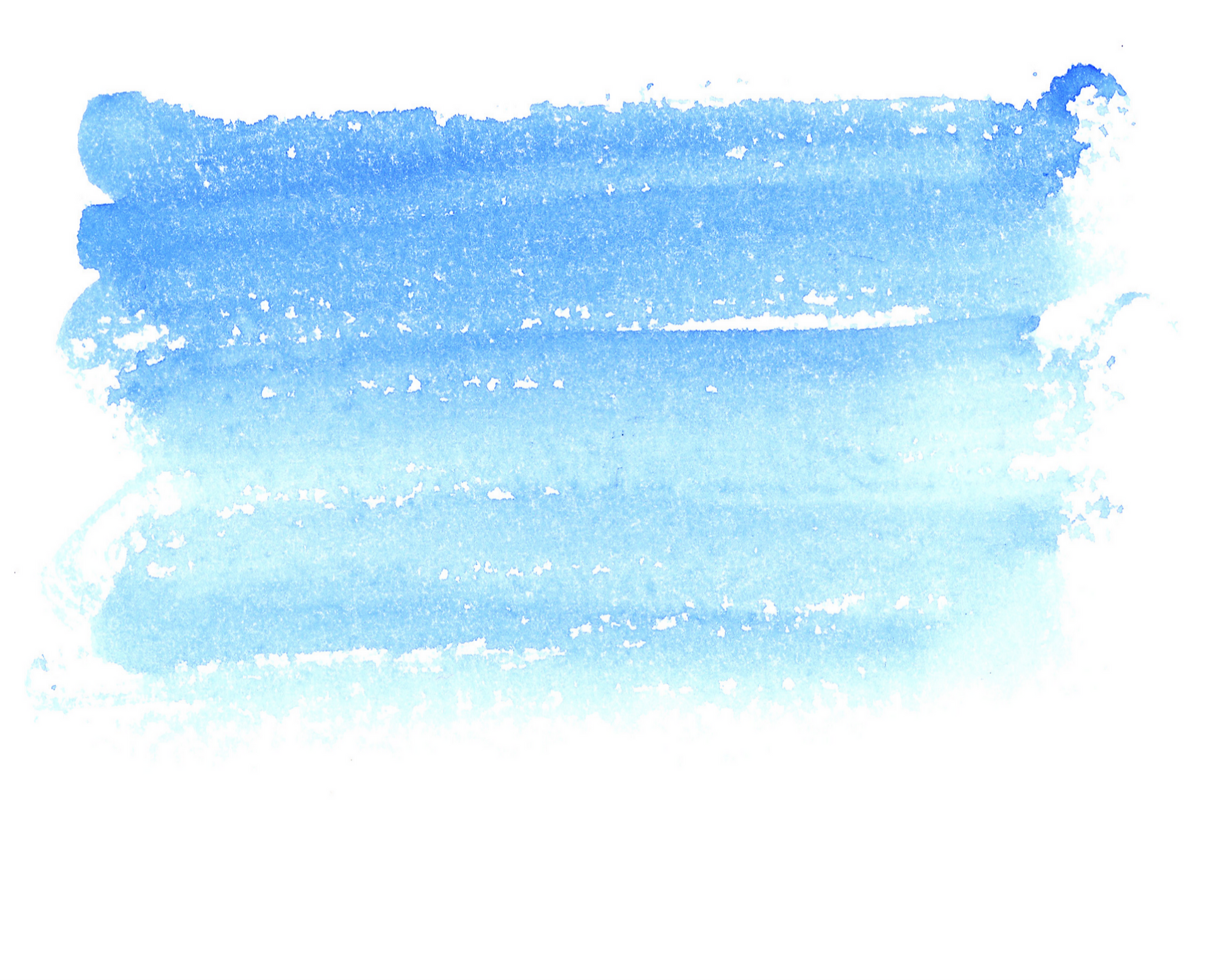
なつの景色
「おはよう」
今日、あたしは、「林田さん係」になってしまった。
道徳の時間のことだ。担任の立花先生が、黒板の真ん中に「心の病気」ときれいな字で書いてから、言った。
「今日は、みんなに考えてもらいたいことがあります。林田恵さんのことです。二年生になってから一度も教室には来てないから、顔を見たことが無い人もいるかもしれないね。林田さんが保健室登校をしているのは、みんな知っているよね? だけど、本当は林田さんも、この二年A組の教室で、みんなと一緒に、楽しくお勉強したいんです」
窓から生ぬるい午後の風が入り込んで、あたしの頬をなでていく。
立花先生のウエーブのかかった茶色い髪と、白のロングスカートが、ふわりと揺れた。
ああ、なんかあくびが出そう。眠いなあ。
「勉強が楽しいわけないじゃん。あーあ。俺も保健室でさぼりてーよ」
お調子者の田川がちゃちゃを入れると、みんながくすくすと笑った。
田川はチビのクセに人一倍、度胸のある男子で、うちのクラスのマスコット的存在だ。
うるさいと思う時もあるけど、こんな時は、田川にちょっぴり感謝したくなってしまう。
立花先生は田川をちらりと睨んでから、かまわずに話を続けた。
「林田さんは、心の病気なの。心が、ちょっと風邪をひいているのね。それで、教室にいると、苦しくなってしまうときがあるの。でも、みんなが林田さんの病気を理解して、励ましてあげれば、きっと少しずつでもよくなるから……林田さんが早くみんなの輪の中に入れるように、お手伝いしてくれる人はいないかな?」
教卓から身体を乗り出すようにして、立花先生が生徒一人一人をゆっくりと見回した。
とっさに、みんなが先生から目をそらす。
あたしも慌てて机の木目を見つめた。
冗談じゃない。
今の友人関係だけでも、いっぱいいっぱいなのに、保健室登校の子とつきあわなきゃいけないなんて、面倒すぎるよ――。
こんな時、後ろの席で良かったと思う。
あたしは、たくさんの背中に隠れるようにして、こっそり周りの様子をうかがった。
斜め前に座っているリエに目をやると、先生の話なんてどうでもいいと言わんばかりに、一心不乱になにか投げている。
ああ、あれ消しゴムのカスだ。
消しゴムのカスは、リエの前の席、サヤカの背中に当たって、落ちた。よく見ると、サヤカの白いブラウスの背中には、消しゴムのカスがたくさん、くっついている。
リエが振り返りあたしを見て、桜色の薄い唇を引き上げて笑った。
そんなことをしている時でも、リエの笑顔は可愛い。
あたしもつられて、曖昧な笑いを浮かべた。
サヤカはハブられている――。
二週間前までは、あたしとリエ、マリナ、サヤカの四人でいつも一緒に行動していた。
かわいくて、気が強いリエは、あたし達のグループのリーダー的な存在だ。
先生の受けもいいし、男子とも仲が良い。きれいな栗色の髪。短いスカートからすらりと伸びた足。履いているソックスだって、トーゼン学校指定のなんかじゃなくて、ブランド物だ。ブラウスのボタンを外して、いやらしくない程度に胸元を見せているのもカッコいい。
こういう崩した着こなしは、二年生になった頃から女子がこぞってやりだしたけれど、リエはその中で、抜きんでて垢ぬけていた。 リエの髪型や持ち物を真似している子だって、何人か見かける。
マリナも、こっそりリエの真似をしてる一人だ。
リエが唇にグロスをつけたり、ブランド物のポーチを持っていたりすると、
「あっ、それ可愛い。どこで買ったの? ふうーん。そうなんだあ。あたしも実はそういうの持ってるんだよねー。学校にしていくのイケナイかなって思ってたんだけど、リエがやってるならやろうかなあ」
なんて言って、数日後にはちゃっかり、同じグロスをつけて、同じポーチを持ってくる。
正直なこと言っちゃうと、マリナの顔はリエと違ってあんまり可愛くない。
地味なあたしにこんな風に思われたくないだろうけど、でも、あたしは、自分が大した顔じゃないってことくらい、十四年生きてきたんだもん。ちゃあんとわかってる。自覚してる。
だけどマリナは、どういう訳か本人の自己評価はかなり高いらしい。
二年生になったばかりの時、マリナがリエに話しかけているのを聞いたことがある。
「このクラスの女子って地味じゃん? だから、あたしやリエみたいな子って目立つっていうかあ。リエがいて良かったよお。同じレベルの子がいて安心したー」
「レベル」マリナが好んで使う言葉だ。
はたから見ていれば、マリナとリエが同じレベルのルックスだなんて到底、思えない。
だけど中学校の一クラスという閉鎖されたこの空間では、マリナみたいに強気で図々しい子が強者だ。
クラスの大人しい女子のことをやたらと見下しては、「ブス」「キモイ」と文句をつけるマリナのこと、正直言って、あたしはあんまり好きじゃない。
マリナにとっても、リエと仲良くしたいだけで、あたしのことはリエのおまけ程度にしか思ってないだろうけど――。
あたしがリエと仲良くなったのは、ほんの些細なことがきっかけだった。
新しい顔ぶれの並ぶ教室に、一年生の頃の仲良しグループが一人もいないことを知って落ち込んだあたしは、席でこっそり、生徒手帳に挟んだ切抜きを眺めていた。
その時、突然、後ろからリエが話しかけてきたのだ。
「ねえ、もしかしてそのバンドのファンだったりする?」
あたしの切り抜きを指差して、興奮した様子でリエが言った。
「う、うん。そうだけど、もしかして、高野さんも?」
「うん! チョーかっこいいよね。でも周りで知ってる子がいなくってさ。ラッキー! 同じファンの子がクラスにいるなんて」
あたし達は同じバンドのファンだったのだ。
まだあんまりメジャーとは言えないバンドで、周りには誰も知ってる人がいなかったから、びっくりしたけれど、すごく嬉しかったっけ。
あたしとリエはそのバンドの話で盛り上がり、すぐに仲良くなった。
こんなきっかけがなかったら、ルックスは地味。勉強も運動も、中の中。茶髪にしてみたいけれど、勇気がなくて迷ってるような、そんな冴えないあたしとリエが友達になることなんて、なかったかもしれない。
だからあたしは、あのバンドのファンで良かったと心から思う。リエみたいな子と友達になれたのが、なんだか、すごく誇らしかった。
そして、リエとマリナとあたしの後を、金魚のフンみたいにくっついて歩いてたのが、サヤカだ。
いつもアニメのキャラクターみたいに髪の毛を高い位置で二つに結んでいて、ふわふわの天然パーマが、一人じゃ何も決められない性格を表しているみたいに、あっちへ、こっちへとはねている。
あたし達はよくサヤカをからかった。
背が低くて、色白ぽっちゃり体系だから、「子豚ちゃん、って感じ」とマリナにからかわれて、むくれていたこともあった。
少しトロくて、甘えん坊で、淋しがりで。もしもあたしに妹がいたら、こんな感じかなと、たまに想像したりもした。
やたらと腕を組みたがったり、どこへ行くにもついてきたり、ちょっと、うっとおしいなと思う時もあるけど、腹が立つ程じゃない。
そう。あたし、わかってた。
ハブられるほど悪いこと、あの子は何にもしていないって……。
最初に言い出したのはリエだったと思う。
サヤカが、風邪で休んでた日のことだ。
いつも後からついてくるサヤカがいないと、何だか寂しいかも。そんな風に思っていた授業の合間の休み時間、リエが言った。
「今日ってサヤカ休みかあ。なんかさ、いつもと感じちがわない?」
「あ、うんうん。そうだよね」
ちょっと、寂しいよね。そう言おうとした時だった。
「なんかあ、ショージキ、すっきりしちゃうって言うか。あ、こんなこと言っちゃかわいそうか。でもさあ、あの子って、たまにうっとおしいんだよね」
そのつぶやきに、マリナが、
「そうそう、やっぱりそうだよね! あたしもいっつも思ってたんだ」
と大げさに騒ぎ立てた。
胸がドキドキ、高鳴った。
たしかにサヤカは同い年なのに甘えてるところ、あるかもしれない。だけど。リエとマリナが、そんな風に思っていたなんて……。
「そもそも、あの子って、あたし達とはレベルが違わない? ちょっと見た目、小学生みたいだしさあ。いっつもくっついて来るしさ。
あたし実は、あの子と一緒に歩くの、恥ずかしいー。なーんて、思ってたんだあ」
「やーだ、マリナってば、言いすぎ」
「でも、本当のことだもん」
「ね、ユッキーはどう思う? やっぱり、うざいよね。サヤカ」
二人が同時に、あたしを見た。
ユッキーというのはあたしのあだ名。野村由紀だからユッキー。
このあだ名で呼ぶのは、リエとマリナ、それから……サヤカの三人だけだ。
「あ……うん……」
どうしよう。
言わなきゃ。何か返さなきゃ。
「……たしかに、甘えてるところ、あるしね……うっとおしいかも、だよね」
二人が途端に笑顔になった。
「でっしょー? やっぱユッキーもそう思ってたんだ」
「だよねえ。あたしとリエが思ってたんだもん。ユッキーだって思ってるよね」
「あー、今日、思い切ってみんなに言ってみて良かったあ。あたし、サヤカって、だーいっきらい」
そのリエの言葉が、合図だった。
悪口はサヤカの普段の行動から始まり、喋り方、テストの点数、外見……。尽きることなく、繰り広げられる。
「あの子この前の教室移動でも、モタモタしててトロかったしさあ」
「あ、だよね。急かしたら教科書、落としたりして。見てるこっちが恥ずかしかったあ」
「何やるにしても、トロいよねー」
あたしも言うんだ。もっと。もっと。
「……サヤカの髪型ってダサいよね。あの天パー。理科室にあるスチールウールみたいじゃない?」
あたしの発言に、二人が大ウケする。
「わー。ユッキーったら言うー」
「わかるわかる。あたし、いつもツッコミたかったもん」
良かった。ウケた。
ほんの少し、罪悪感で胸が痛む。だけど、ウケたことの方が何倍も嬉しい。
……あたし、悪い子なのかな?
じゃあ、リエもマリナも悪い子?
それなら、あたしは悪い子の仲間でいい。
悪口って、強力な呪文だ。言えば言う程、あたし達の結束を強くしてくれる気がする。
サヤカが本当に嫌いな訳じゃない。
だけど、みんなで悪口を言ってると、本当にサヤカがすごく嫌な子のように思えてきて。自分達はとっても正しくて、強いような気がしてくる。
もっと言わなくちゃ。
もっと、もっと――。
最初に感じていた罪悪感は、いつのまにかすっかり小さくなってどこかへ消えてしまった。
次の日から、サヤカはハブになった。
あたし達は、泣きそうになってオロオロするサヤカを見ては、くすくすと笑った。
二人に合わせて笑ってみせながら、あたしの胸の中に、罪悪感と、優越感と、それからもうひとつ、言いようのない恐怖感が広がっていくのがわかった。
もしも、あたしも、ハブにされたら――。
ううん。あたしは大丈夫。うまくやってるもの。だけど……。
されないって、言い切れる?
不安はじわじわと胸に広がっていく。
学校は戦いの連続。気を抜いたら、やられてしまう。
あたしは、絶対にサヤカみたいにはならないんだ。
だから、保健室登校の女の子に構っている余裕なんて、これっぽっちもないんだ――。
「立候補してくれる人、いないかな?」
立花先生が小首を傾げて、みんなを見回す。
「お嬢、うざっ」
誰かがつぶやく声が聞こえた。お嬢というのは生徒がこっそりつけた、立花先生のあだ名だ。
二十五歳には見えない童顔で、制服を着たら、たぶん生徒と見分けがつかないだろう立花先生は「キレイごと」が大好きで、何かとズレたことばかり提案してくれる。
例えば、「全員で長縄とびにチャレンジしよう」だとか、「一日一つ、詩を書いて、帰りの会で発表する」だとか。
思いつきに振り回されるあたしたちは、いい迷惑だ。そのくせ、サヤカがハブになってることには全く気がついていないんだ。
キレイな世界に生きている、鈍感なお嬢様先生。そんな皮肉を込めて、お嬢。
そのお嬢な立花先生は、しらけムードのみんなを見渡して小さくため息をつくと、
「じゃあ、そうねえ。保健委員の人にお願いしようかな。えーと……」
そう言って、黒板の横に貼ってある紙に目をやった。嫌な予感。
「保健委員は……野村由紀さんね。野村さん、お願いね。仲良くしてあげてね」
そんな訳であたしは「林田さん係」に任命されてしまったのだ。
林田さん係の仕事は、週に二回、保健室で林田さんと一緒に給食を食べること。それだけ。
あたしは給食のトレイを持って、保健室へと向かう。
二年A組の教室は四階。保健室は一階にあるから、パンやスープがこぼれないようにトレイを運んでいくのは、結構、大変だ。
一歩ずつ、慎重に階段を降りるあたしの頭の中を、さっきリエ達と交わした会話がぐるぐると回った。
「まあ頑張りなよ、結構、ユッキーとその子、相性良かったりしてね。仲良くなれるかもよ。私は無理だけど」
憂鬱な気分でトレイを持ち、教室を出ようとしていたあたしに、マリナがニヤニヤ笑いながら話しかけてきた。
「合うわけないよ。そんな子と」
マリナったらひどい。あたしは少し、ムキになって言い返す。
そうよ、合うわけないじゃない。
保健室登校の子だもん――。
私とは、違うもの。
リエが息を弾ませて駆け寄ってきた。
「ねえねえ、今、林田さんのこと聞いてきちゃった」
「聞いてきたって、誰に?」
「ほら、カオリやマイコって、一年の時A組じゃん。林田さんと同じクラスでしょ。でね、一年の時もやっぱり、林田さんってクラスでチョー、浮いてたんだって。最初は仲の良い子もいたみたいなんだけど、友達を裏切ったとかなんかで……」
「えー、裏切ったって……何それ?」
「詳しいことはカオリ達も知らないらしいんだけど……ひどいことしたってウワサ。で、みんなからハブられてさ。いつの間にか教室に来なくなっちゃったんだって」
「そうなんだ……」
「やっぱり、保健室登校してるような子だもん。どっかちょっとおかしいんじゃない。いきなりキレちゃったりするとかさ。気をつけた方がいいよ。ユッキー」
そう言うリエの表情は、言葉とは裏腹に何だかイキイキしていて、余計にあたしは不安になった。
「もう。リエったら、脅かさないでよお」
笑ってかえしたものの、やっぱり、気になる。
林田さん。一体、どんな子なんだろう――。
「失礼しまーす……」
片手で保健室のドアを開けると、白衣を着た保健の島谷先生が、
「野村さんね。話は聞いてるわ」
と、あたしの手からトレイを受け取り、部屋の中央にあるテーブルの上に置いてくれた。
「野村さん、この子が林田さん。二人は初対面かしら? 仲良くしてあげてね」
テーブルにはもう一つ、トレイが置かれている。そのトレイに置かれたパンとまるで睨めっこでもしてるみたいに、女の子が一人、パイプ椅子にうつむいて座っていた。
この子が、林田さん……。
「じゃあ先生は職員室で食べてるから……何かあったら、呼んでちょうだいね」
そう言い残すと、島谷先生はそそくさと保健室を出て行く。
さあ、二人きりで思う存分友情を育んで下さい。そんなところか――。
きっと立花先生がアレコレ企んでるに違いない。ミエミエの先生達のやり口に、舌打ちしたくなるのをこらえて、あたしはテーブルへ向かった。
心をどんよりと灰色の雲が覆っていく。
本当なら今頃は、リエ達とバカ話をしながら給食を食べてるハズなのにな――。
あたしがいない間、リエとマリナは何を話してるんだろう。もしかして、あたしの悪口を言ってたりなんてこと……ないよね。
座ろうとパイプ椅子を引くと、キィときしむ音がして、林田さんが顔を上げた。
大きな瞳。白くてふっくらした頬、肩にかかるストレートの黒い髪。おばあちゃんちに飾ってある、日本人形みたいだ。
「あ、はじめまして……だよね。あたし、同じクラスの野村由紀……です。これからたまに林田さんと給食、ここで食べることになったから。その、よろしくね」
林田さんは、白い頬を少し赤らめて、小さく頷いた。
「よろしく……あの、ごめんね、野村さん」
「ごめんねって、どうして?」
「立花先生に言われたの。『あなたには、話し相手が必要なの。私が何とかするから』って。私、クラスの人達には迷惑をかけたくなかったのに……ほんとは教室で仲良い子と食べたいよね、ごめんね」
あたしの目をしっかりと見て、申し訳なさそうに言う。
ここに来るまでに想像していた「保健室登校の女の子」は、暗い子、ワガママな子、話が通じない子、そんなイメージばかりだったけど、実際の林田さんはそのどれとも違った。
あたしのことを気遣ってくれているのがわかる。
もしかすると、意外といい子なのかもしれないな。
「別に……いいよ。さ、食べようよ」
「うん……」
「いただきます」
「いただきます」
「……」
「……」
しまった。話題がない。
レーズンパンをちぎっては口に運びながら、何か話さなくてはとあたしは考える。沈黙って、苦手だ。
「えっと……あのさ、林田さんは、どうして保健室登校なんてしてるの?」
言ってから、後悔した。
直球すぎた。大体ここで深刻な悩み相談なんかされたところで、あたしに何ができるっていうんだろう……。
先生に言われて、イヤイヤここにいるだけの、あたしなのに。
「あっ、言いたくなかったら、言わなくていいよ。変なこと聞いてゴメン」
林田さんが黒目がちの大きな瞳をまばたきさせてあたしを見た。
唇をきゅっとひきしめる。まるでたくさんの言葉が出口を求めているのに、それをかたくなに押さえつけてでもいるように。
そして、たった一言、
「教室が、こわいの」
そう言ったきり、目を伏せた。
それからは、ただ二人とも黙って、給食を食べ続けた。
教室に戻ると、リエがキョーミシンシンという顔をして話しかけてきた。
「ユッキー、林田さんと一緒に給食食べたんでしょ? どうだった? どんな子?」
「うん、おとなしい子だった。でも結構かわいかったし、性格も良さそうな……」
「ふうーん……」
リエのしらけた空気が伝わってきたから、あわてて付け足す。
「あ、でもやっぱ暗いっていうかさ、全然、話題もないし、ずーっと二人で無言で食べてたんだよ。もー困っちゃったよお」
リエが満足そうに頷いた。
「だよねえー。保健室登校してる子となんてさ、何話すんだって感じだよね。お嬢もほんっとロクなこと考えないよ。リエだってユッキーと給食食べたいのにさあ」
「ほんとほんと、こういうのってひどいよねえ」
あたしもリエに合わせて相槌を打つ。
突然、あ、そうだ。とリエが手を叩いた。
「リエも一緒に保健室で食べようかなあ。保健室登校の子、見てみたいし。なんかちょっと、面白そうじゃん」
指先で栗色の髪をもてあそび、ニッと笑うリエの顔を見ながら、あたしはなんだか胃が重くなっていくのを感じていた。
さっきのレーズンパンと一緒に、何か重い物、飲み込んじゃった気がする――。
次の日には、リエも一緒に保健室で食べることになった。
「私も林田さんのこと、元気づけてあげたいんです」
リエの言葉に、立花先生は手を叩いて喜んだ。
「あなたみたいに優しい子がいて、先生とっても嬉しいわ。ぜひ行ってあげてちょうだい」
立花先生って単純だ。それとも、本当はどうでもいいのかな?
どうでもいいから、何にも見てないのかな。
保健室では、テーブルを挟んで林田さんと向かい合わせに、あたしとリエが座った。
「あたし、高野理恵。リエでいいよ。よろしくね」
林田さんは、ちょっと驚いた顔をしてから、何も言わずに小さく頷いた。
「いっただきまあす」
リエの明るい声が保健室に響く。
「林田さんさあ、いつから保健室登校してるの?」
フォークの先でプチトマトを刺しながら、リエが言った。
「一年生の……二学期から」
「ふうん、なんで? 誰かにいじめられてるとか?」
「別に……」
それきり、唇をきゅっと一文字にして、林田さんは黙ってしまった。昨日と同じ。
「やあだ、せっかくこうして食べにきてあげてるのにさあ。無言でいられると困っちゃうんだけど」
リエがあたしに目くばせしてきた。困ったなんて言っているけど、顔は笑っている。
「そんなんだからクラスで浮いちゃうんだよ? なんていうかさあ、空気読めないっていうかあ。もーちょっと林田さんも努力した方がいいんじゃない?」
林田さんが持っていたスプーンを置いて、うつむいた。
もう、あたし達の方を見てくれない。
「ちょっとお、どうしよー全然喋ってくれないんですけど。ヤバくない? っていうかあたし恨まれちゃう? チョー怖いんだけど」
リエがわざと小声になって、あたしにささやいた。
「ね、イマドキあのスカート丈ってありえなくない? 三つ折ソックスとか。すごくない? 笑えるんだけどー」
リエの目の奥に意地の悪い光がきらめいて、あたしに語りかける。
さあ、笑え。笑いなさい。と。
「あは、ほんとだ……」
それなのに。
どうしても顔の筋肉がひきつって、あたしはうまく、笑えなかった。
教室に戻ると、リエが「あーあー」と投げやりに言って、伸びをした。
「もっといじりがいのある子ならいいけどさ。正直つまんなーい。喋んないしー、暗いしー。もう保健室行くの、やーめたっと」
歌うように言うと、
「あ、その雑誌見せてー」
ファッション雑誌をめくっている女子の輪の中へ入っていく。
あたしも、と言おうとした時、ふと席に座っているサヤカと目が合った。サヤカは慌てて目をそらす。
昼休みの騒がしい教室の中、サヤカの周りだけがひっそりとした重い空気に包まれていた。サヤカは何度も消しゴムで、ノートをこすっている。
リエやマリナが、サヤカが席にいない時を狙って教科書やノートに落書きしているのは知っていた。
机の上をチョークの粉まみれにしたり、男子が持ってきたエッチな雑誌を置いておいたり。
そんな幼稚で陰険なイタズラが、どれだけサヤカを効果的に傷つけるかということを二人はよくわかっている。
あたしも何度か、一緒に落書きをした。そうしないと、二人から浮いてしまいそうだったから。
サヤカが再び顔を上げ、今度は目をそらさずに、あたしを見つめた。
ねえ、助けてよ。ひどいよ。
そんな声が聞こえてくるような気がして、立ちすくむ。
いじめは良くない。
そんなこと、わかってる。でも、世の中はキレイごとなんかじゃ生きていけない。
サヤカも林田さんも、みんなの輪からはずれてしまったの。けど、はずれたんだから、仕方ないのよ。
あたしはちがう。
輪の中で、生き残るんだ。
手の平に爪がささって痛い。いつのまにか、両手を強く握りしめていた。
「やだあ、これすっごい面白いよ。ユッキー、一緒に見ようよお」
リエが呼んでる。
行かなくちゃ。
「なになに、見せてえ」
慌ててあたしは、手を振った。
開いた手の平から、何かがこぼれて落ちていくような気がした。
次の週からは、また、あたしと林田さん二人きりの保健室での食事になった。
「リエ、もう来ないって」
あたしがそう言うと、
「そうなんだ……」
ほっとしたような、それでいて、どこか悲しそうな顔をして、林田さんがつぶやいた。
「その……あの子、悪い子じゃないんだけどさ。林田さんとは、タイプが違いすぎるかもね」
「……うん。いいの」
何だか今頃になって、あたしは無性にリエに腹が立ってきた。
リエはいいよ。行きたくないって思ったら、すぐに止められるんだもん。でも、この先ずっと、林田さんに会わないといけないあたしはどうなるの? 今だって、この間のリエの態度のせいで、気まずいったらありゃしないじゃない。
……もちろん、実際、本人に言う勇気なんかないけどさ――。
「いただきます」
「いただきます」
スプーンとフォークの音だけが、静かな保健室に響く。
林田さんはさっきから、あたしの方を見ない。
嫌われたのかな。そう思ったら、なぜだか少しせつなかった。
リエと一緒に笑ったクセに、あたしって、勝手だ……。
「……」
「……」
やっぱり今日も、沈黙。
閉められた窓から、かすかに聞こえてくる蝉の声だけが、静かな保健室に満ちていく。
この先ずっと、週二回、こうして二人で黙ったまま、給食を食べないといけないのかな。
考えただけでうんざりしてくる。
あたしはリエと違って、「林田さん係」だから逃げられない。それなら、せめて、楽しく会話しながら食事したい――。
もっとも、林田さんはもう、あたしと話したくないかもしれないけれど……でも、まだ、嫌われたと決まったわけじゃないし。
とにかく、話題。何か話題をふってみよう。
いつもリエ達と、何の話をしていたっけ。先生の悪口、好きな男子のこと……ううん。もっと楽しい話がいい。
「ねえ、林田さん。田川って知ってる?」
林田さんが身体をびくっと震わせて、驚いた顔であたしを見た。
「……うん、一年生の時、同じクラスだった……」
「あいつさ、今日、立花先生に向かって何て言ったと思う?」
「……あの、わかんない……あの、ごめんね」
またリエの時のように責められると思ったのか、しどろもどろになって謝る林田さんを見ていたら、なんだかひどく悪いことをしてる気分になってきた。
ちがうよ。あたしは、楽しい話をしたいんだよ。
鼻からすっと息を吸い込むと、一息に喋った。
「それがねえ。『お母ちゃん!』って言ったんだよ。お母さんじゃなくて、お母ちゃんだよ。その後、耳まで真っ赤になって、必死でごまかしてんの。もークラスのみんな、大ウケだったんだから」
少し緊張しながら、林田さんの表情に注目してみる。
「……」
林田さん、ぽかんとしたままだ。
ヤバイ。失敗だったかな……。
と、ふふっ、小さな笑い声が聞こえた。
林田さん、笑ってる。
「ね、おかしいでしょ」
「うん……田川君、一年生の時も同じことしてた」
「えーっ! 二回目なんだ。あいつってマザコン? でもママじゃなくてお母ちゃんってとこが、田川だよねえ」
「ふふふ」
笑顔の林田さんは、今までみたどの表情よりも、かわいく見える。
「田川君、一年生の時もみんなの人気者だった。今もやっぱり、そうなんだね」
「んー。人気者っていうか、マスコット?」
「でも、すごいよ。みんなに好かれてるもん……」
「あ、もしかして」
「え?」
「林田さん、田川のこと……」
「え、ち、ちがう。絶対ちがう」
「あはは。そんなに否定しなくても、わかってるって」
「もお、野村さん……」
あたし達は顔を見合わせて、笑った。
なんだ。林田さんって、普通の女の子なんだ――。
テーブル近くの大きな窓から、夏の日差しがあたし達を照らしつける。外はいい天気だ。
そういえば教室でリエ達と食べていた時は、おしゃべりに夢中で、外なんか見てなかったっけ。
「あ、あの子が来てる」
林田さんが窓の外を見て目を輝かせた。
「あの子って?」
「ハト」
窓のすぐ向こうには、花壇が並んでいる。その中に生えている、あたしの背丈と同じ位の高さしかない細い木に、ハトが一羽、とまっているのが見えた。
「ハトさん、待っててね」
ガラガラと林田さんが窓を開けると、クーラーの効いた保健室に、むわっとした熱気が広がった。
「野村さん、ごめんね。暑い?」
「ううん、いいけど……何するの?」
「これ、あげようと思って……」
「パン? ハトに?」
「うん」
林田さんが食べかけのパンをちぎって窓からまくと、ハトはあわてて枝から降りようとして、バランスを崩して地面に体を打ちつけた。よく見ると、左側の羽がボロボロだ。
「ああ、もう。あわてないでいいのに」
顔をしかめて、林田さんが言う。
「ケガしてるんだね、あのハト」
「うん、あんまり高く飛べないみたい。一度パンをあげたら、よくここに来るようになったんだ」
ハトは体勢を立て直すと、すごい勢いでパンをつつき始めた。きっとおなかがすいていたんだろう。
「もっと、ゆっくり食べればいいのに」
嬉しそうに夏の日差しの中で笑う林田さんは、何だかとても、生き生きして見える。
「あ、あっちにもハトがいるね」
十メートル程向こう、照りつける太陽を反射して、ギラギラと立ち並ぶ鉄棒のそばに、たくさんのハトが群れをなしている。
「この子、ケガが治ったら、群れの中に戻れるのかな」
林田さんが、ケガしたハトを見ながら、ぽつりとつぶやいた。
「うん……たぶん、また群れに戻って飛ぶんじゃないかな」
「……そうだよね」
実際、ハトのことなんてよく知らないけれど。
そんな事、わからない。なぜだかそうは、言えなかった。
ふいにハトの群れが、合図でもしたように、いっせいに羽を羽ばたかせて飛んでいく。
あたしはそっと、隣に立っている林田さんを見た。
なんだか、悲しそうな横顔だった。
日が経つにつれ、あたしと林田さんは少しずつ、打ち解けてきた。
と言ってもほとんどは、あたしの話に林田さんが笑ったり、頷いたりしているだけだったけれど。
最初は嫌でたまらなかったはずの保健室での時間が、いつの間にか、あまり嫌ではなくなっていた。
あたしは林田さんの前では、なぜだかとても楽でいられたから。
林田さんは、大きな瞳をまばたきさせながら、言葉の一つも聞き逃すまいと、一生懸命にあたしの話を聞いてくれる。
子供の頃、読んだ本で、聞き上手な女の子のお話があったっけ。女の子に話を聞いてもらうと、それだけで、人々は癒されていくんだ。
それ、今はちょっとわかる。
リエとマリナと話す時、あたしはいつも聞き役だ。あたしは二人みたいに、ウケる話ができないから。
リエが笑ったら、笑って、マリナが怒ってたら、一緒に怒る。それで良かった。うまくいってた。
でも、林田さんと話をしてると、自分でも不思議なくらい、たくさんの言葉が口から飛び出してくる。
知らなかったな。
あたしって、結構おしゃべりだったんだ――。
保健室で給食を食べるようになって、三週間が過ぎた頃だ。
林田さんに、クラスの男子のバカ話を話していた時、スカートのポケットが震えた。
ケイタイにメールが一通。リエからだ。
「保健室での給食の味はどお?」
とだけ書かれている。
「もう、リエったら」
あたしはすぐに、適当な文章を並べて返信した。何でもいいんだ。「あたし達って友達だよね?」それを確認する為だけの、やりとりなんだから。
送信ボタンを押した後、ふと、林田さんがあたしのケイタイをじっと見ているのに気がついた。
校則違反が気になるとか、かな……。
校内へのケイタイの持ち込みは、禁止されている。先生に見つかったら没収だ。だけど一部の生徒達は、こっそり持ってきて使っていた。あたしも、その一人。
前にリエが、
「学校で使えないとか、つまんないじゃん。音鳴らさなきゃ大丈夫だって。みんなでメールしようよー」
そう言ったら、マリナもサヤカもケイタイを持ってくるようになった。
そうなると、当然あたしだって、持っていくしかない。校則違反で先生に怒られるよりも、あたしにだけメールが回ってこないことの方が、ずっとずっと、怖いもの。
「林田さんって、ケイタイ持ってる?」
「……ううん、持ってない……」
「ふうん。欲しいとか思わない?」
「ん……あの、前は持ってたんだけど……」
「えっ、じゃあなんで今は持ってないの? 没収されたとか?」
「それは……」
林田さんがうつむいて黙りこむ。
ああ、あたし、また余計なこと、言っちゃったかも。
そう後悔しはじめた時だ。林田さんが顔を上げて、何かを決心したみたいな目で、あたしを見た。
「ほんとはね……一年生の時は持ってたの。入学祝いに、お母さんに買ってもらったんだ」
ずっと外に出ないように押さえつけていた言葉達を一言ずつ解放していくみたいに、ゆっくりと話しだす。
林田さんが自分のことを話してくれるのは、初めてだ。ケイタイを握りしめる手が、じわりと汗ばんだ。
「中学に入って、仲良しの子も何人かできて。毎日すごく楽しかった。みんなとメールアドレス交換して、たくさんメールして……」
たった一年前のことなのに、まるでずっと昔の出来事を思い出すみたいに、林田さんは懐かしそうに言う。
「でも。ある日変なメールが来たの。『不幸のメール』ってタイトルだった。内容は、このメールと同じ内容を一週間以内に三人に送らなければ、友達も好きな人も、離れていきます。っていうの……」
「ああ、あれ……」
そのメールのことは知っている。一時期、かなり出回っていたメールだ。
幸い、あたしの所には送られてこなかったけれど、誰に送ろうかなんて悩んでる子や、こんなの気にしない、と言いつつ、送信した相手を恨んでた子もいたっけ。
「私、ショックだったんだ……」
林田さんが目を伏せる。長いまつ毛が震えていた。
「そのメール送ってきたの、私が一番仲良しの友達だった。次の日問い詰めたら、開き直ったみたいに、あんたも送ればいいじゃん。って言われたの」
「それで、林田さんは、誰かに送ったの?」
林田さんは小さく首を振る。
「私は、送れないよって、その子に言った。友達にこんなメール、送れない、知らない人にも送りたくないって……それからその子は私のこと、無視するようになった。良い子ぶってるって、言われてたみたい。それで、気がついたら……」
「……ハブになってたんだ」
林田さんが頷いた。
「それから、教室に行くのがすごく怖くなったの。教室に入ろうとすると、吐き気がして、お腹が痛くなるの。足が動かないの。このままじゃいけないって、わかってる。だけど、どうしたら治るのか、わからないの……」
ぽたりと、透明のしずくが給食のトレイの上に落ちた。
「……」
何も言えなかった。「がんばれ」とか、「負けないで」とか、そんな、おざなりの言葉を口にするのは簡単だけれど、今それをしたら、自分を心底嫌いになりそうだと思った。
「……ごめんね、こんな話。給食がまずくなっちゃうね」
手で涙をぬぐって、林田さんは無理に笑顔を作ろうとする。
「結果的には、ほんとに不幸のメールの通りになっちゃった……結構効力、あるのかな」
効力なんて、あるわけない。
ただのメールにそんな力ないってこと、みんなわかってるはずなのに、それでもメールは止まらない。
あたしだったら、不幸のメールを誰にも送らずにいられただろうか。送った相手を、恨まずにいられただろうか。
「あ、今日はあの子、来てないね。天気が悪いからかな」
わざと明るい調子で、林田さんが窓の外を見て言った。
窓の向こうには、灰色の空が広がっている。
雨が降りそうだな、と思った。
放課後になると、雨はぽつりぽつりと降り出して、校庭の地面の上にたくさんの水玉模様を作った。
あたしとリエとマリナ、三人で連れ立って校門を出る。少し前なら、サヤカも加わって四人で帰っていたはずだ。けど、もう誰もそのことには触れない。
マリナがビニール傘を手に持ち、あたしとリエが両脇から、無理やりに顔を突っ込んだ。
「急に降るんだもんねー。マリナはエライよ。置き傘持ってるんだから」
リエがマリナの顔を覗き込んで言う。
「もう、二人ともくっつきすぎ。狭いよ」
マリナがあたしの肩だけを、傘の外へと押しやった。
「ほらあ、出た出た」
「ちょっと、マリナってば、ひどくない?」
「冗談だって」
そんな他愛ないやり取り。
でも、あたしは、マリナの目が笑ってないのを知ってる。
「あ。あれ見て」
リエが急に立ち止まると、前を指さした。
青い傘。傘から覗く、ストレートの黒髪。きちんとひざ丈まであるスカートに、三つ折のソックス。
「林田さんだよ」
リエがあたしを見た。
「声、かけなくっていいの?」
リエの声に意地の悪い響きがこもる。
「別に……いいよ。それよりさ……」
会話をそらそうとする間もなく、マリナが口を挟んだ。
「へー、あの子がそうなんだ。ユッキーは毎週話してるから、もう結構仲良いんじゃないの?」
「ううん、そんなことないって……」
言いながら、お願い、早く行ってしまって。と祈るような気持ちで林田さんの背中を見た。
「リエは一緒に給食食べたことあるけど、やっぱ変な子だったよー。チョー暗かった。保健室登校なんてしてる子だもん。いかにもって感じ」
リエの得意げな声が、カンにさわる。
林田さんとの距離はどんどん縮まっていく。二人とも、わざと早く歩いているんだ。あの子に会話が聞こえるように。
お願い。林田さん、早く向こうに行っちゃってよ。
そんなあたしの気持ちなんてまるで知らずに、林田さんはのんびりと歩き続ける。後ろからきた生徒達が、何人も林田さんを抜いていく。
もう一メートル程の距離まで近づいた時、リエが息を吸い込んで、口の横に手を添えて大きな声で言った。
「大体、保健室登校する子なんかと、本気で仲良くする訳ないってえ。ボランティアだよ、ボランティア。ねっ、ユッキー」
ちがう。やめて。
そうじゃない。
ボランティアなんかじゃない。
林田さんが振り返る。
大きな瞳があたしを見る。
「やめてよ!」
とっさに、叫んでいた。
頭の中が真っ白だ。
今の声……。
あたしが、言ったの?
一瞬、時間が止まったみたいに、リエもマリナも動かずにいた。
だけど次の瞬間、二人の尖った視線が、あたしを刺した。
「なに? なんでマジになってんの?」
「へー。ユッキーって、あんな子の肩もつんだ」
マリナが唇をゆがめて笑う。
「あ、ちが……ちがうの……」
あわてて取り繕ってみようとしたけど、うまくいかない。
どうして、あんなこと言っちゃったんだろう。
「もしかして、保健室で給食食べるうちに、仲良くなっちゃった?」
「ユッキーはさあ、もともと、あたし達とはレベルが違うんだって」
行こ行こ、とマリナがリエの腕をひっぱった。ビニール傘があたしの頭の上をすりぬけていく。冷たい雨が頬にあたる。
リエが振り返り、笑って言った。
「ユッキーも、保健室登校しちゃえば?」
二人は私を置いて、走りだす。
ビニール傘と、甲高い笑い声は、あっというまに遠くなって、林田さんの大きな瞳だけが、その場に残って、あたしを見つめていた。
もう、やだ。
何もかも、いやだ。
走り出していた。林田さんが、後ろから何か言ってるような気がしたけれど、かまわずに走った。
足にスカートに、水がはねる。
雨の音が、強くなったような気がした。
翌朝、教室に入るとすぐに、リエとマリナの姿を探した。
昨日のこと、謝ろう。
謝って、今まで通り、仲良くするんだ。
林田さん係も、誰かほかの人に代わってもらえるように先生にお願いしよう。
――そうすれば、全て元通り。あたしは平穏な生活に戻れる。
ファッション雑誌を眺めている二人を見つけて、あたしは、いつものように挨拶をする。
「リエ、マリナ、おはよう」
語尾がかすかにかすれてしまった。頑張れあたし。ちゃんと言わなきゃ。
「二人とも昨日は、ごめん。あたしね……」
言いかけたあたしの言葉をリエがさえぎった。
「ねえ、さっきからブツブツ、うるさいんだけど。誰か近くにいるのかなあ」
きょろきょろと大げさに辺りを見回す。目の前にいるあたしの姿が、まるで見えていないみたいに。
「ええー。誰も見えないよ。もしかしたら、幽霊かもよ? 保健室の」
マリナが横目でちらりとあたしを見て、笑う。
さあっと顔から血の気が引いていくのがわかった。指先が、痺れたように冷たくなっていく。
心臓がドクドクとマラソンの後みたいに早く脈打って、息ができない。苦しい。
なのに頭の中は妙に冷静で、認めたくない現実をあたしにつきつける。
――ああ、あたしにも、ついにきたんだ。
マリナが椅子から立ち上がると、手を振った。
「おはよー。サヤカあ、こっちこっち」
ドアの前でサヤカがカバンを持ったまま、呆然としてあたし達を見ている。
どうしてハブのあたしに声をかけるの? そんな顔だ。
「ほら、こっち来なってば」
リエの手招きに引き寄せられるように、サヤカがゆっくりと歩いてくる。その目に、かすかな希望の色が浮かびあがっていた。
「今までごめんねー。サヤカ」
「なんかあ、あたし達、勘違いしてたんだよね。本当にハブにするべきが誰か、わかったってわけ」
二人があたしを見ながら、ニヤニヤと笑う。
「えっ、あの……」
まだ事態がよく飲み込めていないサヤカが、不安気な表情で、あたし達の顔を見比べた。
「だからあ、あんたのハブ、終わったの。これからはまた、よろしくね」
マリナがなんでもないことみたいに、軽い調子で言った。
ナメられてんだよ、サヤカ。今までハブにして、散々ひどいことしたクセに、軽い「ごめん」の一言でおしまいだなんて。
虫が良すぎるじゃない。怒っていいのよ。
それなのに。サヤカは怒るどころか、
「……良かったあ。もう、ハブじゃないんだあ。うれしい」
まるで泣いてるみたいな情けない顔で、笑った。
「ねえ、ここに誰もいないよねえ? さっきから変な声がするんだけど、どう思う?」
リエが椅子に座ったまま、サヤカを上目づかいに見る。
サヤカはとまどった表情で、おそるおそる、視線をあたしに向けた。
お願いサヤカ。何か言って。
あたしは祈るような気持ちで、サヤカの目を見つめた。けど。
「……そうだね、誰もいないね」
サヤカはそっと、あたしから目をそらした。
それから、あたしは、リエ達の新しいハブになった。
あたし達の様子がおかしいと気づいた他のグループの女子の中には、気遣って声をかけてくれる子もいたけど、やっぱりみんな、どこかしらそっけない。「面倒なことに巻き込まれたくない」そう思っているんだろう。
ハブになって最初のうちは、シカトされるだけで済んでいたけれど、嫌がらせは少しずつエスカレートしてきた。
朝、登校するとあたしの上履きがない。
仕方なく、先生達の下駄箱に置いてある、お客さん用のスリッパを借りて教室へ行く。
教室のドアを開けた途端、女子の笑い声が一瞬止まる。たくさんの視線があたしを刺して、通り過ぎていく。
そして、さっきとは種類の違う、ひそやかな、ねちねちと絡みつくような笑い声。
リエ達があることないこと、周りに言いふらしているから、もう他のグループの子もあたしに近づかない。ううん。近づかないどころか、一緒になって笑っている。
男子だってもうとっくに気づいているだろう。
「なーんか、女子って面倒そうなのな。次の生贄はお前かあ」
田川がすれ違いざま、あたしをからかった。
――恥ずかしい。恥ずかしくて、消えてしまいたい。
席に着こうとすると、机には、
「死ね」「ばーか」「ブサイク」
そんな幼稚な言葉の羅列が、黄色や赤のチョークで殴り書きされていた。
ポケットからハンカチを出して、あたしはそれを素早く拭き取る。お母さんがアイロンをかけてくれた花柄のハンカチが、あっという間にチョークの粉まみれになっていった。
――こんなの全然、平気なんだから。
そうよ。時間が経てばハブも終わる。みんなが飽きるまで。もしくは、「次の生贄」が現れるまで。……それまでの辛抱だ。
だけど、ナイフでえぐられたみたいに胸が痛い。
喉がジンと熱くなり、あたしはつばを飲み込んだ。
泣くもんか。
きゃはは、と近くで大きな笑い声が上がった。
見なくたってわかる。リエ達だ。
その笑い声に、サヤカの声も混じって聞こえる。
サヤカ。
あんたはハブられた時、あたしのこと、どう思ってた?
憎かった? 恨んでた?
今は、ざまあみろって思ってる?
サヤカはきっと、もう答えてはくれない。
あたし、どうしてあんなことしてたんだろう――。
家では、何事もなかったように振る舞っていた。お母さんも、お父さんも、何も気がついてない。それでいい。
夕食を食べて、テレビを見て、お風呂に入ってから、自分の部屋へ行き、ベッドに入る。
今夜も眠れない。
最近は、ずっとそうだ。夜になっても眠れない。
夢を見たくなかった。教室で毎日聞こえてくる耳に障る笑い声は、夢の中までもあたしを追いかけてくる。
「ユッキーも、保健室登校しちゃえば?」
そう言って、リエが笑う。
夜中に何度も、目を覚ました。
天井がぐるぐるまわる。めまいが止まらない。
怖い。もう一度目を閉じたら、あたし、そのまま冷たくなってベッドの中で死んでしまうのかもしれない。
だけど。怖いって思う反面、死んじゃうなら、それもいいかも。って気持ちもある。
もう、疲れちゃったし。
死んじゃえば、誰かに傷つけられることも、誰かを傷つけることもなくてすむ。
少なくとも、もう学校には行かなくていいんだ。
あたしは胸に手をあてて、ゆっくりとまぶたを閉じる。
神様。このまま、あたしを死なせてください。
眠りながら、安らかに心臓が止まりますように。
もう、何も考えたり、悩まなくってすみますように。
このまま、眠りながら、死ぬんだ……。
目が覚めると、朝になっていた。
結局今日も、生きてる――。
がっかりしたのと、ホッとしたのが混ざった気持ちで、パジャマのままリビングへ向かうと、お母さんが、オレンジジュースをコップについでくれた。
「おはよう、由紀」
「ん……おはよ」
いつもの朝だ。あたしはテレビを見ながら、トーストをかじる。一口だけ、かじってから、お皿に置いた。もう、食べたくない。
心って、体のどこにあるんだろうって、前に考えたことがある。
理科の教科書にも載ってない。誰も見たことがないのに、誰もが知ってる、あると言われている、部分。
それが、今はわかる。たぶん、肺と胃の間あたり、その奥だ。
そこがこの頃ずうっと、じんじんと痛くて、何をしていても、その痛みが治まらない。テレビを見ていても、ご飯を食べてても。
「あらやだ、もう食べないの?」
お母さんのノンキな声が、今日は少しだけ気に障る。
「ダイエットしてるの。この頃太っちゃって」
テレビを見ているフリをしながら、だるそうに答えた。
お母さんの目、見れない。
「あなた位の年でダイエットなんて、良くないのよ。朝ごはんはちゃんと食べなきゃダメ」
お母さんが果物ナイフを手に取ると、リンゴを剥き始めた。
「せめて果物だけでも食べなさい。倒れちゃうわよ」
「いらないって」
本当に、何にも食べたくないんだもの。
体が「食べ物は要りませんよ」って言ってる。これも自殺の一種なんだろうか。
お母さんが、リンゴを剥く手を止めて、あたしを見た。
「由紀、最近ちっとも食べないわね。どこか、体調悪いんじゃないの。それとも、学校で何か……」
「うるさいなあ!」
あたしは両手でテーブルを叩くと立ち上がった。
「ほんとにダイエットしてるだけだよ。もういい。学校行く」
食べかけのトーストをお皿に残して、自分の部屋に戻り、制服に着替える。
「行ってきます」
玄関で靴を履きながら、ふてくされたように言うと、
「行ってらっしゃい」
お母さんが悲しそうな顔で、見送ってくれた。
保健室には前と変わらず、給食を食べに行っていた。
教室に居場所がなくなった今、保健室で林田さんと話すひとときだけが、あたしが唯一、安らげる時間だった。
「今度、野村さんの絵を描いていい?」
牛乳を飲んでいた時、林田さんにこう言われて、吹き出しそうになってしまった。
「林田さん、絵を描くんだ」
「うん、あんまり上手くないけど、描いてると楽しいの」
目を細めて笑う。最近、林田さんは口数が多くなった。少し明るくなった様にも見える。
保健の島谷先生には、
「野村さんのお陰よ」
って言われたけど、あたしは知ってるんだ。
林田さんが、時折、何か言いたげな、心配そうな瞳であたしを見つめているのを。
あの雨の日のことを林田さんは聞いてこないけど、あたしがどんな状況の中にいるのか、きっと気がついてる。
だから、少しでも気を紛らわせようと、明るく振る舞ってくれているんだ。
「林田さんの絵、見てみたいな」
きっと、優しい、きれいな絵を描くんだろうな。
見てみたい。心からそう思った。
「あの、じゃあ……今度、うちに来ない?」
「えっ」
「あ、イヤだったらいいんだ。ごめんね、いきなりこんなこと言って」
「ううん、行く。行きたい」
「本当?」
「今度じゃなくて、今日でもいいかな」
「うん。大丈夫……あの、本当に、大した絵じゃないの。期待、しないでね?」
「ううん、思いっきり、期待する」
ニッと笑ってみせると、林田さんもくすくすと笑った。
「野村さんがうちに来るなんて、夢みたい」
「絶対行くよ」
あたしは力強く頷いていた。
放課後、林田さんがノートに描いてくれた簡単な地図を頼りに、彼女の家を探した。
一緒に帰れば話は早いんだけど、「私と一緒に帰らない方がいいと思う」と言う林田さんに、あたしは「そんなことない、あいつらに見られようが、どうでもいいよ」と言い切ることもできない情けない人間だったからだ。
林田さんの家は、学校近くの大通り沿いに建っていて、すぐにわかった。チャイムを押すと、出てきたのは優しそうな女の人だった。
「まあまあ、野村さんでしょ? 恵からいつも話は聞いてるわ。大変お世話になっているみたいで……さあ、おあがりになって。ゆっくりしていってね」
さあどうぞどうぞ、とあたしの肩を押す。
玄関に入ると、廊下の突き当たりにあるドアが開いて、林田さんが顔を出した。
「あっ。いらっしゃい、野村さん」
ピンクのシャツに、デニムのスカートを履いた林田さんは、いつもより幼く見える。
「ほんとにねえ、こうして恵の友達が来てくれるの、久しぶりだわ。コーヒーと紅茶、どっちがいい? あっ、甘いものは好きかしら、美味しいクッキーがあるのよ、それとも……」
「もう、お母さんったら、野村さん困ってるじゃない。おやつなら後で取りに行くから。ね、野村さん、私の部屋行こう」
お母さんと話している姿も、学校で見る林田さんとは違う。明るくて、ちょっと甘えん坊の女の子っていう感じ。
もしかしたら、これが本当の林田さんなのかもしれないな。
階段を上がると、小さなピエロのマスコットがぶらさがったドアの前で、林田さんが立ち止まる。
「散らかってるから、恥ずかしいんだけど……」
ドアが開く。
「わあ……」
部屋に入り、あたしは、声をあげた。
壁じゅうに貼られた、絵。
額に入っているもの、紙のまま貼られているもの、様々だ。淡いタッチの水彩画で、風景や動物が描かれていた。あのケガをしたハトの絵もある。
どの絵も明るいブルーやグリーンを基調に描かれていて、まるで光が射す海底にいるみたいだ。
「すごく、きれい。部屋中で色が踊ってるみたい」
「ほんと? ありがとう……」
林田さんの顔が赤くなる。
「人間だけ、まだ描いたことがないの。描こうとしたんだけど、うまくいかなくて……だけど、野村さんに会って……描いてみたいって思ったの」
どきりとした。
あたしの絵。どんな絵になるんだろう。
ここにあるような、きれいな絵には、きっとなれない。臆病で、弱虫で、ずるい、あたしの絵。どんな絵になるの?
「野村さん?」
黙って立っているあたしの顔を、不安そうに林田さんが覗き込む。
「あたしね、クラスでハブられてるの」
唐突に、言葉が出た。
最初の言葉が出てしまうと、後は糸でつながれてるみたいに、するすると言葉が飛びだしていく。止まらない。
「でも、私もサヤカをハブってた。ひどい嫌がらせもした。仕方ないことなんだって思ってた。林田さんのことだって、最初は保健室登校の子だってバカにしてた……」
喉が熱い。
泣いちゃいけないと思っているのに、どんどん涙が溢れてくる。
だけど、気持ち良い。
「あたしは弱くて、卑怯な人間なの。いつだって、自分さえ良かったらいい、そういうずるい人間なんだよ。林田さんに描いてもらう資格なんか、ないよ」
林田さんは強く首を横に振ると、まっすぐにあたしを見た。
「私、野村さんがいてくれて、学校に行くのが楽しかった。野村さんがいつも、教室で起こった色んな話してくれるのが嬉しかった」
「……」
「怒ってくれたよね。雨の日、あの二人に。野村さんは、優しい人だよ。優しくて、強い人だよ」
ちがうよ。林田さん。
あたしは泣きながら叫んでいた。
「あたし、優しくなんかない。強くなんかないよ。あの後だって、あたしは二人に謝ることばかり考えてた。林田さん係だって、やめようと思ってたんだよ。ハブになるのが怖かったから……」
「野村さん……」
林田さんの肩越しに、あのハトの絵が見える。
傷ついた一人ぼっちのハトは、寂しいだろうか。辛いだろうか。早く群れに戻りたいって、思っているだろうか。それとも、本当はぜんぜんそんなことなくて、一人ぼっちでもたくましく、楽しく生きているのかもしれない。
そうだったら、いいのにな。
「仲間はずれが怖いのは……私もそうだよ。きっと、みんなそう。だけど、野村さんは私の為に、本気で怒ってくれた。私ね、涙が出る位、本当に嬉しかったの。ああ、こんな人もいるんだって、思った。私も変わりたいって、思ったの」
「変わるって?」
「私ね……二学期になったら、学校、やめるの」
「やめるって……転校しちゃうの?」
声が裏返った。そんなの嫌だ。
せっかくこうして色んなこと、話せるようになったのに。
「フリースクールに行くの。その学校、絵に詳しい先生がいて……一度見学に行ったんだけど、素敵な絵を描く先生だった」
林田さんが薄い冊子を見せてくれた。
フリースクールの学校案内らしい。
「この先生だよ」
林田さんが指差したのは、壁一面に描かれた大きな絵の前で笑っている、太った女の人の写真だ。
「うわ、ハデ」
「うん、凄いよね」
壁には、うねるような赤や青や黄の原色の洪水の中に、たくさんの動物と人が力強く描かれている。
その前で、紫色のアフロヘアに、目玉みたいな模様のたくさんついた、蛍光ピンクのワンピースを着た女の人が、大口を開けて笑っていた。キョーレツ。まるで、女の人も絵の一部みたいだ。
「その先生ね……壁の絵をじっと見てた私に、『絵は好き?』って聞いてきたの。はい。って答えたら、次に『人は好き?』って聞かれて……私、答えられなかった。野村さんのことは好きだけど、学校のみんなは、怖い」
「うん……」
あたしも怖い。リエ、マリナ、サヤカ、クラスのみんな。
仲良しだったのに。クラスメイトなのに。
今はみんな、怖い。
「黙ってる私に、先生が言ったの。『いつか、広い世界を見てごらん』って」
「世界……?」
「これも、その先生がくれたの」
林田さんが数枚のポストカードをあたしに渡した。外国の写真だ。
黒い肌に白い歯をむきだしにして笑う男の子。民族衣装らしいドレスをまとった女の人達。帽子をかぶった金髪の女の子。
「これがインドで、タイ、こっちはスウェーデンって言ってたかな。先生、写真も好きで、旅行に行く度にたくさん撮ってくるんだって」
「へえ。みんな笑ってるね」
「ふふ、すぐ友達になっちゃうんだって言ってた。写真を撮る時には、変な顔をして笑わせるのよって言って、私にもすっごい変な顔してみせるんだよ。あれは、笑わずにはいられないよ。野村さんにも見せてあげたいな」
林田さんがくすくすと笑う。
「先生ね、『これからたくさん色んな物を見て、色んな人に触れてごらん。世界を見てごらん。きっと、あなたにしか描けない素敵な絵が描けるよ』って、そう言って、笑ってくれたの。太陽みたいな笑顔だった」
世界。
そんなの、遠い言葉すぎてピンとこないけど――。
あたしはポストカードの女の子を見つめた。
いくつ位だろう。もしかすると、あたし達と同じ位かな。
あたしと林田さんがこうしている間にも、地球は回って、世界は動いてて、たくさんの人達が生きている。
普段はぜんぜん、意識してないけど。考えてみても、あんまりピンとこないけど。でも、それは事実だ。
その中にはあたし達と同じ、十四歳の女の子もいて、やっぱり友達のことで悩んだり、眠れない夜を過ごしたりしているんだろうか。
「素敵な先生だね」
胸がぎゅっと痛くなる。
林田さんは、もう笑っていなかった。
「私ね、ずっと、思考停止してたの。何も考えたくなかった。考えるのが怖かった。本当は学校、休みたかった。でも、お母さんの悲しそうな顔見たくなくて……だから保健室には行ったの」
「ん……」
あたしもそう。本当は、学校なんか行きたくない。休まないのは、親に心配をかけるのが辛いから……ううん。親に、いじめを受けてるなんて知られたくない。知られるのが、恥ずかしいからだ。
「フリースクールのことは、お母さんが見学を勧めてくれてたんだけど……行く気になれなかった。人が怖かったの。どこに行ったって同じなんだって思ってた。けど、野村さんに会って……私、このままじゃいけないって。変わらなきゃって思ったんだ」
そっか、林田さんは、ちゃんと新しい道を見つけたんだ。
「もう保健室で、会えないんだ……」
寂しい。そう言いたかったけど、口にしたらいけない気がしてあたしは唇を噛む。
「私、弱虫だから……何もなかったみたいに、教室に戻って授業受けるの、もう無理だと思う。ねえ野村さん。学校を辞めるのは、悪いことなのかな。私、ただ逃げてるだけなのかな……」
今度はあたしが首を振った。
何が逃げることで、何が立ち向かうことなのか、あたしにはよくわからない。
だけど林田さんは戦ってる。ずっと、戦ってるんだ。
あたしはぽろぽろ出てくる涙を拭いもしないで、ただ、首を振り続ける。
「あ、あたしの絵。期待してる……から……」
うわずった声で、やっとそれだけ言えた。
「うん……。夏休み中に、きっと届けるね」
林田さんの声もいつの間にか、涙声になっていた。
夏休みが終わり、二学期最初の日。あたしは朝早く目が覚めた。
リビングに行くと、お母さんが「今朝は早いわね」と言いながら、オレンジジュースをコップについでくれた。
「パン、二枚食べられる?」
黙って頷くと、お母さんは嬉しそうに笑う。
お母さん、目尻の皺が増えたみたい。
心配させてごめんなさい。心の中でつぶやいた。
「ごちそうさま」
部屋に戻って制服に着替える。そのまま廊下へ出ようとして、ふと、振り返り、あたしは壁に貼られた絵に向き直った。
「行ってくるね」
絵の中のあたしは、唇をきゅっと結んで、強いまなざしで、あたしを見据えた。
教室へ行くと、いつもと何だか様子が違った。
「おはよう、ユッキー」
マリナがあたしに笑いかける。
「夏休み、どこいったのー? ちょっと焼けた?」
サヤカが二つ結びの髪をゆらして、はねるようにしてあたしの所へやってくる。
どういうこと?
訳がわからず、目をぱちぱちしているあたしに、マリナが少しだけ、ばつの悪い顔をしてささやいた。
「いままで、ごめんね。ユッキー。あたし達、ユッキーを誤解してた。本当に嫌な奴は誰かって、わかりきってたことなのにね」
どこかで聞いたセリフだ。サヤカが唇をとがらせて、上目づかいにあたしを見る。
「そもそもサヤカがハブになったのだって、あの子のせいだもん。ごめんねえ、ユッキー」
よくわからないけど、あたしのハブが終わったらしい。じゃあ。あの子って……。
「ちょっと可愛いからって、調子に乗ってるよね、あの男好き」
マリナが「男好き」の部分を、声色を変えて強調すると、サヤカがうんうんと頷く。
「ひどいよね、マリナの好きな人にベタベタしちゃってさ。夏休み、デートしてたの、見た子もいるって」
「マジで許せないよ。あの女」
マリナがアゴで示した方向に目をやると、リエが男子達と話しているのが見えた。
やだあ、もう。なんて言いながら、嬉しそうに男子の肩を叩いている。
話が終わったのか、教室を見回すリエと目があった。こっちに歩いてくる。
「おはよー二人とも、あれえ?」
リエがわざとらしく語尾を上げた。
「どうしたの? こんな奴と一緒にいるなんて。なんかしちゃった? こいつ」
いつものリエだ。可愛くて、強気で、性格の悪い、いつもの。
「どうしたの? みんな、おはよーってば」
リエはきょとんとして、マリナの目の前で手をひろげて、ひらひらさせる。
マリナがリエを睨みつけた。
「あーあ、なんか変な人がきたよ。サヤカ、ユッキー、あっち行こう。男好きなんかほっといて」
リエの手が、動きを止めた。
サヤカが嬉しそうに合いの手を入れる。
「行こう行こう、男好きな人は、男と話せばいいんだよ」
舌足らずな声が教室に響く。やだあ、男好きだってえ。女子達がちらちらとリエを見て笑った。
リエはようやく事態を飲みこんだのか、真っ青な顔をして立ちすくんでいた。
「行こうよ、ユッキー」
「そうだよ。行こう」
マリナがあたしの腕をひき、サヤカが背中を押す。
ゆっくりと二人の手をはらいのけると、あたしはリエに向き直った。
リエが、あたしを睨みつける。
「あんた、夏休みの間に根回ししたんでしょ? 卑怯な女。サイッテー……」
リエの目が光っている。あたしへの憎しみと恐れで、いっぱいの瞳。
あたしは、ちいさく唇を動かす。
「……」
今、言いたい言葉は、これだけ。
「なによ、聞こえない。ハッキリ言いなさいよ」
リエが叫ぶ。
あたしは胸いっぱいに、息を吸い込んだ。
「おはよう!」
精一杯の大きな声。
教室のみんなが驚いて振り返る。
呆然としてるリエ。
ひきつった笑顔を貼りつかせたままのマリナとサヤカ。
あたしはくるりと三人に背を向けて、席へ向かう。
背中に突き刺さる視線。前までは怖かった。今だって、やっぱり怖い。
だけど、あたしは、あの絵みたいに――。
席に着いて、ひとつ新呼吸。
震える胸を手で押さえ、背筋を伸ばす。
始業のチャイムが鳴り、みんなが席に着き始める。
リエは何だかわからないという顔をして。
マリナとサヤカは何度もあたしを振り返っては、ほんの少し脅えたような表情で。
田川があたしの前を通り過ぎざま、いつものからかうような声で言った。
「やるじゃん。生贄」
吹いてくる風がふわりと頬をなでて、あたしは窓の外を見た。
ほんの少し風が冷たい。
もう、夏が終わるんだ。
誰もいない校庭には、蝉の声だけが騒がしく響いている。
ふと空を見上げると、抜けるような青い空の中、一羽のハトが高く飛んでいくのが見えた。
bottom of page